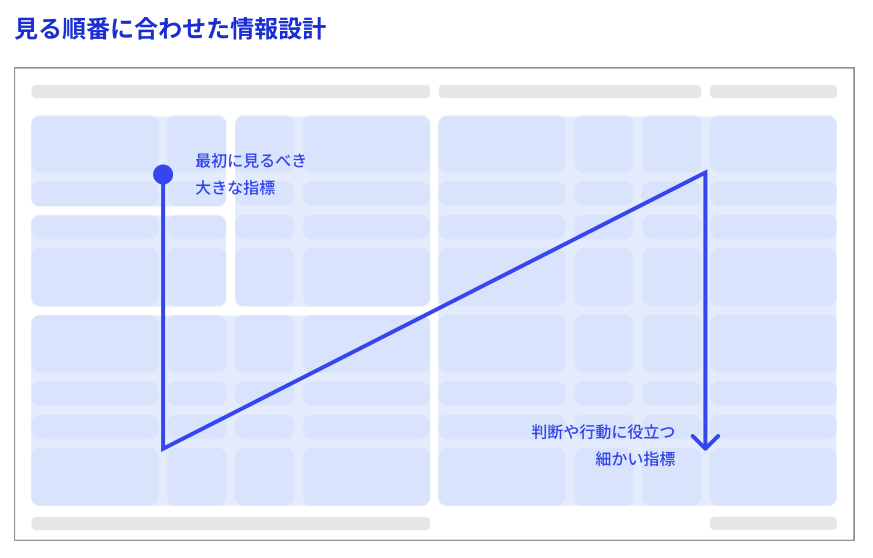デジタル庁が行政や公共機関、民間企業の人々が見やすいダッシュボードを効率的に作るための方法を提供している
内容がとても良かったのですぐ引き出せるようにメモ
ダッシュボードには、2つの類型があるらしい
- 現状を基準と照らし合わせ、異常などに素早く気づき、行動の必要性を判断する「提示型」
- 明確な判断基準がない事柄について、差分を発見したり、その源流を特定して掘り下げる「探索型」
ここでは「提案型」を中心に取り上げている
ダッシュボード作成手順
要件の整理
まず要件を整理する
ここでは、要件定義ワークシートが用意されているので、これを使う
- 目的を定義する
- 制約条件を定義する(パソコンとタブレットサイズに対応する必要がある、重要な指標は多くても3枚以内でまとめる、など)
プロトタイピング
実装前にプロトタイプを作って関係者と話し合う
ここでは、ダッシュボードイメージ作成キットが用意されている
- 載せるべき情報の整理をする(必要な情報の一覧化、グラフ候補の選定)
- 載せるべき情報を選ぶ際の原則
- 目的に則する
- 分解できる
- 違いに気付ける
- 鮮度が高い
- 載せるべき情報を選ぶ際の原則
- プロトタイプを作る(表層の前に、骨格となるレイアウトを決める)
- ダッシュボード設計の原則
- 構造を伝える
- 適切な情報量にする
- 複雑な操作を要求しない
- 比較対象を提供する
- レイアウトは左上から右下に向かって全体が並ぶように配置する
- ダッシュボード設計の原則
- 関係者と話、フィードバックを得る
- 次にステップで進める
- ヒアリングする
- 反映方針を検討する
- 改善する(1に戻る)
- 次にステップで進める
情報表現のポイント
- グラフの種類と選び方

- カラーパレットはデジタル庁デザインシステムから選ぶ
- 組み合わせは以下

- コントラスト比の考え方
- 3:1のコントラスト比を確保
- マウスオーバーかフォーカス時に数字を表示
- グラフの色面領域の近くに数値を記載
- 色覚多様性の考慮
- グラフ設計の原則
- 知りたいことを知れる
- シンプルにする
- 強弱をつける
- 意味のある順列にする
- 待たせすぎない
- 誤解を生まない
- わかりやすく表記する
- 表現を歪曲しない
- データを定義する
- メタ情報を記載する
- 知りたいことを知れる